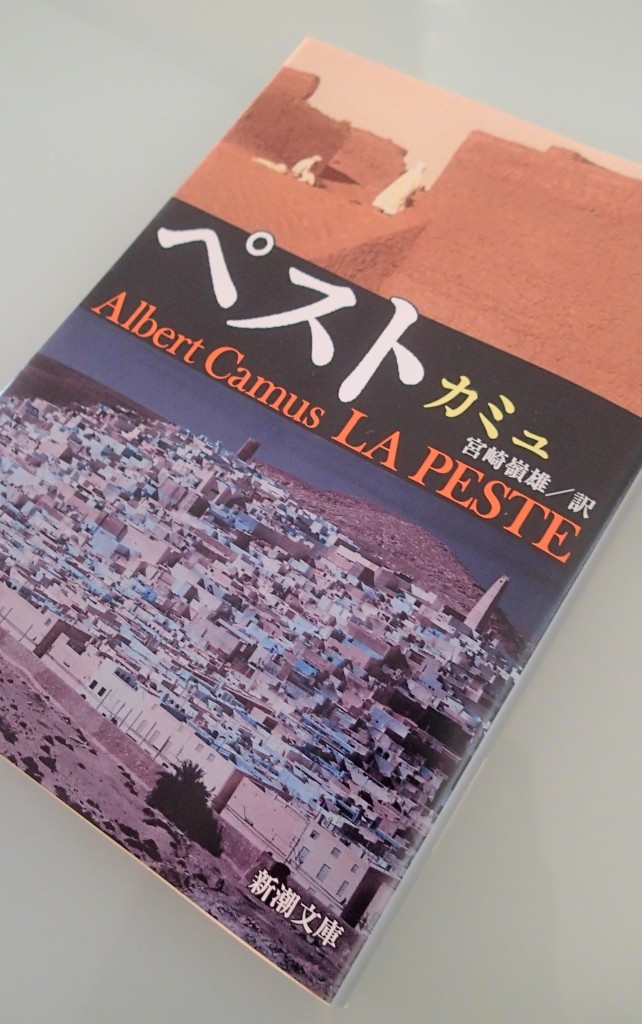2020-08-04(令和2年) 木村良一(ジャーナリスト、元産経新聞論説委員)
■どうして食事中にフェイスシールドを着けるのか
日本プレスセンタービル(東京・内幸町)10階のレストランで、ビールとワインを飲んだ。8月初旬のことで、長い梅雨がやっと明け、眼下の日比谷公園の木々が真夏の陽ざしを浴びて緑色に輝いていた。窓際のテーブルに男女2人の姿を見つけた。向かい合ってではなく、並んで座っている。再び目をやると、2人とも顔に透明なフェイスシールドを着けて料理を食べていた。
どうして食事中にあんなものを着用するのか。フェイスシールドは病院で医師や看護師が感染から身を守るためのものだ。フェイスシールドを着けるぐらい相手の飛沫(唾液や鼻水のしぶき)が気になるというなら、最初から会食などしない方がいいと思う。
こんなこともあった。早朝のジョギングを終え、都庁前の新宿中央公園の中を歩いて自宅に帰るとき、突然見知らぬ女性に「嫌だね。マスクをしないで迷惑だ」と苦情を言われた。女性は大きなマスクを着け、私を睨みつけていた。腹立たしくなって文句のひとつも言ってやろうと思ったが、大人気ないので止めた。
新聞やテレビで連日、新型コロナウイルスの感染者数の増加が伝えられ、だれもがうんざりさせられている。レストランの2人も苦情をぶつけてきた女性も、そんな新型コロナの犠牲者なのだろう。感受性が強く、過剰反応しやすい性格なのかもしれない。
■「危機意識」の振り子が大きく振れている
12年前、論説委員が担当する産経新聞の一筆多論というコラムに「マスクは危機意識の指標」という見出しを付けた記事(2008年5月26日付)を書いたことがある。
その記事では「日本の社会は新型インフルエンザの発生に鈍感で、満員電車の中でマスクも着けずに平気で咳やくしゃみをする人が多い」と指摘し、「皆が危機意識を持ち、その表れとしてマスクを着用する人が増えたらしめたものである」と主張した。
WHO(世界保健機関)や厚生労働省は当時、いやそれ以前からH5N1タイプの鳥インフルエンザウイルスが変異して病原性(毒性)の強い新型インフルエンザが発生すると、世界で7400万人、日本国内で17万人~64万人が感染死すると推計していた。犠牲者の多さはいまの新型コロナのそれどころではない。強毒の新型インフルエンザの発生は、人類にとって最大規模の危機である。感染症の専門家は「新型インフルエンザはいつ現れても不思議ではない」と警告してきた。だが、マスクを使う人は少なかった。
それではいまのマスク着用はどうだろうか。新型コロナの大流行の結果、マスクを着けていないと、外出もできない。コンビニにも入れない。まともに会話もできない。12年前とは大きく違う。多くの人々が危機意識を持つこと自体は評価できるが、振り子が反対方向に大きく振れている。こんな状況になるとは、予想もしなかった。
■「同調圧力」「自粛警察」という負の落とし子を生んだ
ところで私は野外ではほとんどマスクを着けない。外では1万分の1ミリという極小のウイルスは風に吹かれて拡散してしまい、感染など成立しないからだ。確かに息が上がると、後ろを走る人に飛沫が飛びやすくなり、ジョギング中もマスクを着けるべきだとの指摘はある。だが、これまでの取材経験から新型コロナにはそこまでの感染力はないと思う。
マスクを着けないで他人を不快な思いにさせるのは良くないが、社会全体が新型コロナに過剰に反応していないかと不安になる。マスクがないと、周囲の人から白い目で見られる。暗黙の協調を強いられる「同調圧力」である。新型コロナは、この同調圧力のほか「自粛警察」という負の落とし子も生み、「不寛容社会」を強めた。
政府の専門家会議が5月4日に感染予防のための次のような「新しい生活様式」を公表していた。
食事中のおしゃべりは控えめにする。自分の箸からウイルスを広げないように料理は大皿を避け、1人ずつに分ける。電車やバスに乗っているときは会話を控えめにする。人との間隔はできるだけ2メートル空ける。症状がなくともマスクは着ける。
新型コロナの感染は当分の間続き、長丁場の感染対策が求められ、新しい生活様式は無視できない。しかしながらこれを強いることで、負の落とし子を生むようでは本末転倒である。バランス感覚が大切だ。
■感染対策を進めれば進めるほど人の心と心とが遠くなる
緊急事態宣言、3密の回避、ソーシャルディスタンスと感染対策を進めれば進めるほど人の心と心とが遠くなり、社会全体が歪んでいくように思えてならない。感染の拡大を防ぐことは重要だが、病んだ心を元気にすることも必要だ。
メッセージ@penの6月号で、自覚症状もなく進行して気が付いたときには手遅れになる「サイレント肺炎」や私たちの免疫システムが暴走して体内の正常細胞を攻撃する「サイトカインストーム」、それに「血栓症」など新型コロナウイルスに感染することで一部の患者に起きる深刻な病態について書いたが、こうした病態に対する治療方法は次第に確立しつつある。後遺症の問題を指摘する報道もあるが、「風邪は万病のもと」といわれるように通常の風邪やインフルエンザにも後遺症はある。とくに新型コロナだけが後遺症に気を付けなければならないわけではない。
以上、説明したように感染が急増しようと過度に恐れることはないし、過剰に反応する必要もない。
会食中のフェイスシールドや野外のマスクについて過剰反応と指摘したが、感受性が外界に過敏に反応してしまう結果なのだろう。過度に神経質になったり、過剰に反応したりすることで、オキシトシンなどのホルモンの分泌を妨げ、本来の免疫力を弱めてしまうこともあるから気を付けてほしい。
■疫病や戦争が芸術家の感性を高めて名作が誕生する
この半年余を簡単に振り返ってみると、外界からのインパクトはすさまじい。中国湖北省武漢市がロックダウン(都市封鎖)された後、欧米で爆発的に感染者が広がり、WHOがパンデミック(地球規模の流行)と認定した。日本では大型クルーズ船内で感染が起き、市中感染や院内感染も発生した。志村けんさんら著名人も犠牲になった。全国に緊急事態が宣言された。宣言の解除後、再び感染が拡大し、東京都は東京アラートを発動。新宿歌舞伎町など夜の街のクラスター(感染集団)が問題にされ、若者を中心に感染者が急増した。
過剰に反応してしまう一方で、疫病や戦争、災害が芸術家の感性を高め、彼らが素晴らしい作品を生み出すことがある。たとえばアルベール・カミュの『ペスト』(1947年)やパブロ・ピカソの『ゲルニカ』(1937年)がそうだ。『ペスト』は疫病の不条理さと戦い、それを乗り越えようとする人々の姿を克明に描いた小説だ。『ゲルニカ』はスペイン北部の小都市ゲルニカを無差別爆撃したナチス・ドイツ軍を非難した絵画で、ピカソは「スペインを苦悩と死に沈めた軍隊への憎悪を表現した」と語っていた。
カミュやピカソのように感性を研ぎ澄して心や社会を健全に保ちたい。それには感受性をうまくコントロールする必要がある。もちろん、正しく怖がることにもつながる。
―以上―
◎慶大旧新聞研究所OB会によるWebマガジン「メッセージ@pen」の9月号(下記URL)から転載しました。