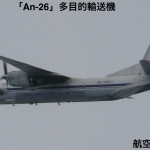米空軍は、今年9月下旬に ”B-52戦略爆撃に対し大規模な近代化改修を実施、7年以内に新型爆撃機として再生する“と発表した。近代化改修には、新しいエンジン、最新のアビオニクス、新しいジャマー(jammers)、新型レーダー、構造部材の交換、などが含まれる。さらに機首下面のセンサー・ポッドを取り外せば外形も変わることになる。(Within seven years, the U.S. Air Force would get modernized reborn Boeing B-52, with new Rolls-Royce engines, new avionics, new jammers, a new AESA radar, and even new structural components. Its exterior profile might be change, if the old sensor pods underneath the nose section are removed.)