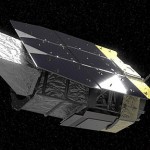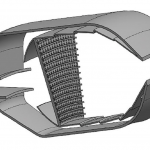
エンジン・メーカーは、ジェット燃料/ケロシンを水素に変えるための研究を長年続けてきた。ヨーロッパ連合(EU)は、民間航空機から出る排気ガスCO2削減の強化を目指し、水素燃料の実用化研究を促進させている。(Engine manufacturers have long studied hydrogen application as an alternative to carbon-based jet fuel. European Union now led decarbonization from aviation industries, by eliminating the CO2, NOX and other impurities from the engine exhaust.)